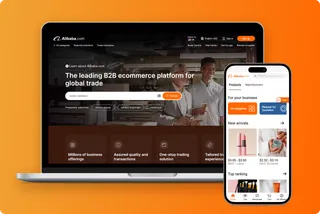首都圏ほど交通網に恵まれていない地方では、車が移動手段の主流となり、広い駐車場を持つ郊外型の大型店舗に客が流出しています。その一方で、昔ながらの商店街では、後継者不足や少子高齢化による客足の減少など多くの課題に悩まされています。
商店街を取り巻く環境は厳しさを増していますが、アイデアや工夫によって活性化に成功している例も多く見られます。元気な商店街をつくる上で必要な要素を、事例とともに解説していきましょう。
新たなコミュニティの場をつくり集客(北海道帯広市)
十勝平野の中心地として栄えてきた北海道帯広市も、郊外へと客足が拡散する中、古くからある商店街の過疎化が問題となっていました。もとの賑わいを取り戻す活性化支援として、平成12年「帯広市中心市街地活性化基本計画」が策定されます。
現在、その一環として効果を上げているのが、「北の屋台」の取り組みです。市民発のこの事業は「帯広の街を良くしたい」という思いから、2年半の調査期間を経て実現しています。屋台の設営は北海道では難しいとされていましたが、市民の情熱もあって若者が集まる人気スポットとして定着しました。
屋台事業は地産地消を売りにして、年間18万人の人出と3億円の売上実績をあげることに成功。昼間の物販やイベントとも連動し、さらなる吸引力の強化を図っています。
少ない投資でも開業できる屋台は新たな起業の場ともなっており、屋台から卒業した後、中心街の空き店舗で本格営業を始める人も出てきています。
空き店舗を活用して街の魅力をアップ(岐阜県岐阜市)
岐阜県岐阜市の美殿町商店街は、婚礼用品の老舗専門店が集まっていることで知られていました。しかし、時代の変化とともにかつての活気が失われ、次第に空き店舗が目立つようになります。
そこで、商店街では岐阜市にぎわいまち公社と合同で創業促進チームを結成し、活性化に着手します。空きビルのリノベーションを行い、「まちでつくるビル」としてクリエイターを誘致して、「ものづくり」の街を復活させました。多くの専門職人が集結していた美殿町商店街らしさを、現代にマッチする形で呼び戻したのです。
成功のポイントとなったのは、「ものづくりの拠点」としてのコンセプトがぶれないように、細部にいたるまで方針を固めたこと、それを実現するためのハード・ソフトの両面から支援を行うインキュベーターの介入があったことなどが挙げられます。
美殿町商店街にはビルの入居者という新たな風が吹き込み、定期的にマーケットを開催するなどの企画が進められています。
ユニークな企画で人が集まる街づくり(大阪商工会議所)
「100円商店街」というユニークな取り組みで、各商店街を活気づかせているのが大阪市です。もともとはNPO法人の発案で始まったイベントが、今では「商店街・賑わいプロジェクト」の一環として各地で開催されています。
街全体が「100均化」するというこのイベントでは、通常は100円以上の価値がある商品を気軽に購入できるため、多くの客で賑わいます。売る物によっては難しい100円というくくりが、各店の工夫によってクリアされているのも注目ポイントです。
例えば、売れ残った本の付録をまとめて100円にしている書店、20%割引券を100円で販売している寝具店など、発想を転換すればどんな店でも「100円商店街」への参加は可能となります。
また、商店街ごとに個性があるのも、「100円商店街」の見どころとなっています。ヨーヨー釣りやゲームができるお祭り型や、詰め放題のできる盛り上がりイベント型など、各商店街がそれぞれに話題を呼び、なじみのなかった客が訪れるきっかけとなっています。
普段は独自でチラシを出せない小さな商店でも、「100円商店街」のチラシに店の名前が掲載されることで、認知度の向上にもつながっています。
商店街ならではの地域貢献が解決の糸口に
少子高齢化の課題に直面する中、地域社会の中心となる商店街に求められる役割は多様化しているといえます。商店の集合体という特性を生かし、そこにある個性に目を向ければ、新たな商店街の方向性が見えてくるかもしれません。
人が触れ合う商店街の良さは、変化する社会にあっても失われるものではありません。ここで紹介された商店街活性化策をヒントに、独自の展開を検討しみてはいかがでしょうか。