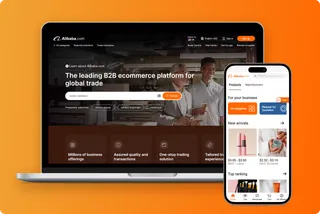初めて海外に自社製品を輸出するとき、海外進出への期待に胸が膨らむのと同時に、「書類や手続き方法に不備はないだろうか」というような不安もつきまとうのではないでしょうか。今回は、初めて製品の輸出や海外へノウハウ・技術の提供を行う際のルールや手続きのポイントについて紹介していきます。
リスト規制
リスト規制とは
輸出などの手続きの際にまずチェックすべきなのが、リスト規制です。リスト規制のリストとは、兵器や武器などの開発に利用されるおそれのある製品・技術を、政令である輸出貿易管理令の別表第1と外国為替令の別表にまとめられたリストのことで、それらに該当する製品を輸出・提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要です。
リスト規制が設けられた背景には、中東地域をはじめとする国際情勢が不安定なことがあります。世界各地では、内戦や反政府運動が起こっている地域や、軍備増強を進めている国などがあります。また、テロリストが世界中で暗躍していることも看過できません。
そこで、大量破壊兵器や通常兵器などを開発している疑惑のある国や組織に軍事転用できる製品や技術が渡らないよう、先進国をはじめとする各国が協調して、国際輸出管理レジームをつくりました。日本もそのレジームに参加したことで、大量破壊兵器などに利用される可能性の高い製品や技術の輸出・提供を規制しようという動きが出てきたのです。
貨物のリスト規制と技術(役務)のリスト規制
貨物については、輸出貿易管理令の別表第1の1~15項に、技術(役務)については、外国為替令の別表の1~15項に記載されています。
<貨物のリスト規制>
項番 | 項目 | 具体例 |
|---|---|---|
1項 | 武器 | 鉄砲・爆発物・火薬など |
2項 | 原子力 | 核燃料物質・原子炉・測定装置・リチウム・エックス線装置・真空ポンプなど |
3項 | 化学兵器・生物兵器 | 軍用化学・細菌製剤の原料(医療用ワクチン、ウイルス)、それらの製剤用製造装置など |
4項 | ミサイル | ロケット・製造装置、ロケット誘導装置・試験装置、ポンプ、ノズルなど |
5項 | 先端材料 | 潤滑剤、冷媒用液体、セラミック粉末など |
6項 | 材料加工 | 軸受等、歯車製造用工作機械等、測定装置等など |
7項 | エレクトロニクス | 集積回路、信号処理装置、高重圧用コンデンサなど |
8項 | 電子計算機 | 電子計算機など |
9項 | 通信 | 通信用光ファイバー、無線通信傍受装置等など |
10項 | センサー等 | 水中探知装置等、反射鏡、磁力計など |
11項 | 航法装置 | ジャイロスコープ等、電波受信機など |
12項 | 海洋関連 | 潜水艇、船舶の部分品・附属装置、水中ロポットなど |
13項 | 推進装置 | ガスタービンエンジン等、人工衛星・宇宙開発用飛しょう体等など |
14項 | その他 | 粉末状の金属燃料、火薬・爆薬成分、添加剤・前駆物質、ディーゼルエンジンなど |
15項 | 機敏品目 | デジタル伝送通信装置等、水中探知装置等など |
リストアップされている貨物には、銃や火薬などいかにもそれらしいものもありますが、一見武器や兵器に結びつくとはわからないようなものもリストに記載されています。そのため、自社の輸出しようとしているものがリスト規制に該当するものかどうかをきちんと事前に確認することが必要です。
キャッチオール規制
キャッチオール規制とは
リスト規制でも15項目の貨物や技術が挙げられていますが、リストに挙げられていないものでも軍事転用される可能性のある貨物・技術があるかもしれません。そこで、抜け漏れが生じないように、すべての品目をキャッチするために作られたのがキャッチオール規制です。キャッチオール規制についても、経済産業省へ輸出許可の申請をする必要がありますが、キャッチオール規制に該当するかどうか、どのように見極めればいいのでしょうか。
ホワイト国・非ホワイト国・懸念国・国連武器禁輸国の違い
キャッチオール規制では、輸出先の国によって、規制の対象かそうでないかが決まります。輸出管理の程度により、輸出相手国を4つのタイプに分類し、輸出管理を徹底している国を「ホワイト国」、武器を輸出してはいけない相手国・地域を「国連武器禁輸国・地域」、それ以外の国を「非ホワイト国」と呼びます。大量破壊兵器を開発・製造している可能性があるため物品や技術の提供が厳しく制限されている国を「懸念国」と言います。それぞれに該当する国・地域は以下の通りです。なお、この中で唯一、ホワイト国のみがキャッチオール規制の対象外となっています。
ホワイト国 | アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 |
|---|---|
国連武器禁輸国・地域 | アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン |
非ホワイト国 | 上記ホワイト国、国連武器禁輸国・地域以外の国・地域 |
懸念国 | イラン、イラク、北朝鮮 |
3つの要件(用途要件・需要者要件・インフォーム要件)
キャッチオール規制には3つの要件があり、いずれかの要件に当てはまる場合は輸出許可が必要になります。
・用途要件
輸出する貨物や提供する技術などが、大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造などに利用されるかどうかを用途の観点から確認するものです。
・ 需要者要件
輸出する貨物や提供する技術などが、大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造などに利用されるかどうかを需要者の観点から確認するものです。大量破壊兵器などの開発・製造への関与が疑われるとして経済産業省が指定する「外国ユーザーリスト」に記載のある企業・組織に輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要となります。
・インフォーム要件
用途要件・需要者要件のほか、輸出する貨物や提供する技術などが大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造などに用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から通知された場合、輸出許可を受けなければなりません。
リスト規制やキャッチオール規制に関する相談窓口
リスト規制やキャッチオール規制に関する相談や質問は、以下の窓口で受け付けてもらえますので、不安のある方は一度問い合わせてみると良いでしょう。
経済産業省 安全保障貿易審査課
Tel:03-3501-2801
qqfcbf@meti.go.jp(リスト規制に関する相談)
anposhinsa-catchall@meti.go.jp(キャッチオール規制に関する相談)
リスト規制・キャッチオール規制の確認フロー
リスト規制とキャッチオール規制の確認の流れを図で表したものが経済産業省のウェブサイトにありますので、こちらを参考にしてみてください。
経済産業省「補完的輸出規制(キャッチオール規制等)輸出許可申請に係る手続きフロー図」

積替規制
積替規制とは
自社製品を輸出しようとする企業にはあまり関係はありませんが、日本の輸出管理制度として積替規制という制度があります。積替規制とは、仕向地が日本以外の国や地域である貨物がいったん日本で仮陸揚げされて別の船に積み替えられるときに、事前に経済産業大臣の許可を必要とする制度です。
たとえば、A国からB国に向けて船舶で貨物を運んでいるときに、たまたま日本の近海でエンジントラブルなどが発生し、日本に寄港していったん貨物を陸に揚げることになった場合などが該当します。このような偶発的な事故だけでなく、C国からD国へ向けて輸出した貨物を、船会社の都合でC国から日本に向かう船に積み込み、日本でD国に向かう船に積み替える、といった形で貨物が仮陸揚げされることもあります。このような場合、日本には正式に貨物が輸入されたわけではないものの、形式上日本からその貨物を「輸出」することになるため、許可が必要になるのです。ただし、洋上で積み替えられた貨物は対象外となります。
許可が必要な場合
仮に陸揚げした貨物が輸出貿易管理令別表第1の1項(武器)にあてはまる場合は、仕向地がどの国・地域であっても輸出許可が必要となります。また、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の2項~16項にあたって大量破壊兵器などの開発などに用いられる可能性があり、かつ仕向地がホワイト国以外の国・地域である場合も、輸出許可が必要です。
仲介貿易・技術取引規制
仲介貿易取引規制とは
仲介貿易取引とは、日本を介して外国と外国が製品を売買したり貸借したりする場合に経済産業大臣の許可が求められることを言います。仲介貿易とは、たとえば日本の企業がE国の企業から仕入れた製品をF国の企業に売るときに、売買契約は日本企業とE国・F国それぞれの企業とで締結するものの、製品自体は直接E国からF国へ輸送することを指します。また、海外で生産した完成品を日本へ輸入することなく直接他国へ販売するときにも用いられます。この特徴から、仲介貿易は主に海外に生産拠点を持つメーカーや商社などに利用されうる取引手段のひとつで、3つの国の間で取引を行うことから「三国間貿易」とも呼ばれます。
積替規制と同様に、貨物が輸出貿易管理令別表第1の1項(武器)にあてはまる場合は、取引を行う国・地域がどこであっても輸出許可が必要となります。また、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の2項~16項にあたって大量破壊兵器などの開発などに用いられる可能性があり、かつ取引を行う両国がホワイト国以外の国・地域である場合も、輸出許可が必要です。
技術の仲介取引規制とは
技術の仲介取引規制とは、居住者(≒日本人)から指示を受けた非居住者(外国人や海外に住む日本人)が海外で技術を提供したり、居住者が外国で修得した技術を他の国で提供したりするときに受ける規制のことを言います。たとえば、G国にある日本企業の現地法人に勤務する技術者が、東京本社からの指示でG国の企業に対して技術研修を行う場合などがこれに該当します。仲介貿易取引と同様に、技術の仲介取引も海外拠点を置くメーカーなどが利用しうる取引手段のひとつです。当該技術が外国為替令別表の第1項に当てはまる場合と、同別表第2項~16項にあてはまり、かつ非ホワイト国へ提供する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。
日本の輸出法令では、食物や木材以外のほとんどの製品・技術が規制の対象となることがおわかりいただけたのではないでしょうか。海外から引き合いがきて実際に貨物などを輸出する際には、製品や技術ごとにリスト規制やキャッチオール規制のどの項目に当てはまるかをチェックするだけでなく、需要者や相手国が規制対象になっていないかどうかも十分に確認するようにしましょう。