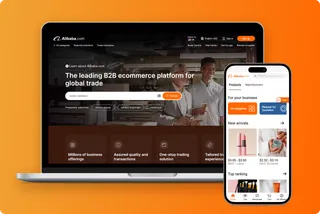米調査機関のピュー・リサーチ・センターの予測によると、イスラム教徒の人口は2010年の16億人から2050年には27.6億人へと増加し、世界人口の3割を占めることが予測されている。また、同予測では2100年までにキリスト教徒の人口を追い越し、世界最大の宗教となることが示唆されている。
日本では2022年10月11日に入国者数の上限が撤廃され個人旅行も解禁されたことでインバウンド需要が戻りつつあるが、中華人民共和国からの観光客がまだ戻ってきていないこともあって、東南アジアからの観光客の姿が目立つこととなった。現状の円安が持続した場合、インバウンド客の増加とともに、インドネシアやマレーシアなど東南アジアのイスラム教国をはじめとしたイスラム圏からの旅行者が増加することが予想される。
国内の労働者をみても、インドネシア共和国(人口2.7億人)・バングラデシュ人民共和国(人口1.6億人)などイスラム教国から来日した人の数が増加しており、労務管理などの面でも、イスラム教徒への対応が重要になってくることが想定される。
本稿では、そうしたイスラム教徒への対応のうち、食の禁忌について考えていきたい。
各宗教の禁忌
食の禁忌があるのはイスラム教だけではない。観光庁の資料では、各宗教の主な避けるべき食品として以下表1のようなものが紹介されている。ヒンズー教徒が牛肉を食べないことはよく知られている一方、イスラム教徒と類似性が高いわりにユダヤ教における食の禁忌が知られてない、といったこともある。
また、かつて日本でも肉食が忌み嫌われていたように、仏教でも禁忌は本来存在する。例えば上の画像1は筆者の家の近所にあるお寺にある碑だが、「不許葷酒入山門」とある。これはかつて五葷といわれるニラやニンニクなど五種の食品が禁忌とされていた名残である。
さらに、食の禁忌が少ないキリスト教でも、一部宗派には断食の習慣があり、断食期間中は一部食品が禁忌になるケースが存在する。
しかしながら、仏教徒で食のタブーがある人はごく稀であるように、宗派や宗教への熱心さなどそれぞれの宗教内でも考え方の違いは大きく、地域間や世代間の違いも大きい。
表1. 各宗教の主な避けるべき食材
宗教 | 避けるべき食材 |
|---|---|
イスラム教 | ・豚肉や豚由来の成分 「ラード」「ブイヨン」「ゼラチン」「ポークエキス」動物性の 「乳化剤」「ショートニング」なども使用しないよう注意する。 ・イスラム法に則った処理が施されていない肉 自然死、病死、事故死した肉を含む。 ・アルコール 料理酒・みりんなども使用しないように注意する。 ・血液 ・うなぎ、イカ、タコ(=鱗のない魚) 教義により禁止されているわけではないが、地域により嫌悪感を示す人が多い。 |
ユダヤ教 (旧約聖書などに根拠を持つカシュルートという食に関する規定がある) | ・豚 ・宗教上の適切な処理が施されていない肉 ・乳製品と肉料理の組み合わせ お腹の中で乳製品と肉料理が一緒になってはいけないため、肉の入った シチューなどが禁忌となる。 ・血液 ・イカ・タコ・エビ・カニ・貝類 カニかまぼこなど連想させるだけで忌避される場合がある。 ・ラクダ・ウサギ・ほとんどの昆虫類・肉食動物など |
ヒンズー教 | ・肉類全般 ベジタリアンの場合。 ・牛肉 神聖な動物として崇拝されるため。 ・豚肉 不浄な動物として忌避されるため。 ・五葷(ニンニク・ニラ・ラッキョウ・タマネギ、アサツキ) 厳格なヒンズー教徒の場合。 |
仏教 | ・肉類 ・酒 ・五葷 |
ジャイナ教 | ・一切の肉食 ・ハチミツ・根菜類 厳格なジャイナ教徒の場合。土を掘り起こして小生物を殺すことを避けるため。 |
(出典:令和2年5月観光庁研修テキストをもとに筆者作成)
ハラールとその基準
一般にハラール食品と呼ばれるが、正確にはイスラム法に則ったものをハラール、イスラム法に則らないものをハラムと呼ぶ。つまり、ハラールは必ずしも食品だけに限った概念ではない。
ハラール食品の判定も、単に食品に成分が含まれているか否かだけではなく、製造工程で豚肉を使っていないかなどサプライチェーン全体に及ぶため、その扱いは複雑である。例えば、ハラールにかかわる事件として有名なインドネシア味の素社のケースでは、最終製品であるグルタミン酸ソーダをつくるための微生物を培養するための培地に使用するたんぱく分解物を他社から購入していた。ところが、仕入先ではたんぱく分解物を生成するための酵素に豚由来の成分を使ってしまっていた。インドネシア味の素社からすると、仕入先の問題であり、かつ自社の最終製品には豚由来の成分は何もないため、かなり間接的な関係しかなかったにもかかわらず、問題となってしまったわけである。
そうした細かい点が問題になることがあるということになると、どこまでを検討していけばよいのか基準がほしくなるが、ハラールか否かの基準はイスラム世界全体で基準が共有されているわけではない。
イスラム教徒が圧倒的に多数の国では、そもそもハラールであることが当然であり、それゆえに基準作りには必ずしも熱心ではない。私は以前、イスラム教国であるバングラデシュに住んでいたが、町を歩いていて山羊や鶏はたくさん見かけたが、豚を見かけたことはない。また、バングラデシュはイスラム教徒ばかりであるので、そもそも普通に生活をしていれば、豚肉が口に入ることやイスラム教徒以外が屠殺した肉に出会うことはない。工場でもハラール食品の製造ラインしかないから、製造工程で交じりあうこともなく、たいていの食品はハラール以外にはなりようがない。
バングラデシュでよく目にする食の禁忌に関連した食品表示としては、緑丸と赤丸のマーク表示があるが、これはバングラデシュ向けではなく、隣国のインドに住むヒンズー教徒向けの表示(緑がベジタリアン向け、赤がノンベジタリアン向け)をつけた製品がバングラデシュ市場でも流通しているものである。
このような状況であるため、ハラールに関する基準や認証はイスラムの中心である中東などではなく、どちらかというと非イスラム教徒も多い東南アジアのイスラム教主体の国家で発達している。
例えば、マレーシアにはイスラム開発局(JAKIM)が定める「ハラール食品の製造、調整、取り扱い及び保管に関する一般ガイドライン」があり、インドネシア共和国にはウラマー評議会(MUI)が定める「ハラール認証の要件」というガイドラインが存在する。
日本国内においても、特定非営利法人日本ハラール協会など複数の団体があり、認証を提供している。
食の禁忌の根拠
イスラム法の法源は最終的には聖典コーランにある。実際にどのようなことが書かれているか見てみたい。
コーランは114の章で構成され、預言者ムハンマドがメッカ又はメディナで受けた啓示が紹介されている。例えば、豚肉を禁止する記述は、第2章「牝牛」や第5章「食卓」に現れる。「牝牛」には「アッラーが汝らに禁じ給うた食物といえば、死肉、血、豚の肉、それから(屠る時に)アッラー以外の名が唱えられたもののみ。それとても、自分から食い気を起したり、わざと(神命に)そむこうとの心からではなくて、やむなく(食べた)場合には、別に罪になりはせぬ。まことにアッラーはよく罪をゆるし給うお方。まことに慈悲の心ふかきお方。」(※出典:井筒俊彦訳コーラン全3巻)と記されている。
また、飲酒を禁止するコーラン上の根拠は、第5章「食卓」にある「これ、汝ら、信徒の者よ、酒と賭矢と偶像神と占矢とはいずれも厭うべきこと、シャイターン(サタン)の業。心して避けよ。さすれば汝ら運がよくなろう。シャイターンの狙いは酒や賭矢などで汝らの間に敵意と憎悪を煽り立て、アッラーを忘れさせ、礼拝を怠るようにしむけるところにある。汝らきっぱりとやめられぬか。」という記述である。
なお、飲酒についてはコーランの記述はやや複雑であり、例えば第16章「蜜蜂」にはアラーの神兆を説く下りにおいて「また棗椰子の実、葡萄などもそのとおり。お前たちそれで酒を作ったり、おいしい食物を作ったりする。もののわかる人間にとっては、これはたしかに有難い神兆ではないか。」と記述されているし、第47章「ムハンマド」では「敬虔な信者に約束された楽園を描いて見ようなら、そこには絶対に腐ることのない水をたたえた川がいくつも流れ、いつまでたっても味の変わらぬ乳の河あり、飲めばえも言われぬ美酒の河あり、澄みきった蜜の河あり。」と記載されているように天国には酒があることが示唆されている。
実は飲酒が禁忌となったのは、ムハンマドがメッカからメディナに移ったヒジュラの後とされていて、ムハンマドが最初の啓示をうけてから10年以上後のことであると考えられている。「食卓」の記述もよく読むと、その啓示までは飲酒をしていたことがわかる内容となっている。なお、通常「蜜蜂」の記述には、飲酒が禁忌となる前の啓示であると注釈がつけられる。
このように後の啓示で内容が変わった例としては、当初礼拝の方角がエルサレムの方向であったものが、後にメッカの方角に変わったことなどが知られている。
上述の記述を参考にすると、問題となっているのは、お酒自体ではなく、酔って神を忘れることであるという解釈もできる。例えば、天国に流れているという酒は地上のものと違い、酔って神を忘れるということにならないから問題ないのだ、というような理解である。そのため、医療用のアルコールや例えば甘酒のような低度数の酒などに関して、イスラム法学内の議論の余地が生まれる。また、トルコワインなどというようなものが存在しているように、国や地域によって、イスラム教でも比較的飲酒に寛容な考え方も存在している。
一般に、イスラム教はコーランを絶対視するために寛容さがない、というイメージを持たれがちだが、コーランは「~をしなさい」という記述だけではなく、「こういう場合は~をしなくてもよい」という記述も多いため、コーランにどのような免除規定があるかを把握しておくと、イスラム教徒と話がしやすくなる場合がある。
例えば、筆者個人の経験として、イスラム教徒の技能実習生が帰国するタイミングがたまたまラマダン中になってしまい、どうしても最後に東京観光をしたいのだが、日中は断食をしたい、と言うことになったケースがある。
8月の東京は猛暑であるために水を飲まないで、あちらこちらに移動するとなると熱中症になる危険が大きいが、本人や国元の家族などはラマダン中だからということで水を飲みたくないという。大変困った状況だが、これを解決したのがコーランの記述だった。上述の「牝牛」章の断食について説いた部分の中には「ただし汝らのうち病気の者、また旅行中の者は、いつか他の時に(病気が直ってから、或いは旅行から帰った後で)同じ数だけの日。(断食すればよい)」という記述があり、旅行中の断食はその分を後で行えばよいことが記されている。これを示して説得をしたところ、ようやく本人も関係者も納得し、安全に東京観光を楽しんでもらうことができたわけである。
コーランをはじめとした考え方の原理を知っておくことは様々な点で助けになると考えてよいだろう。
著者名
齊藤 慶太